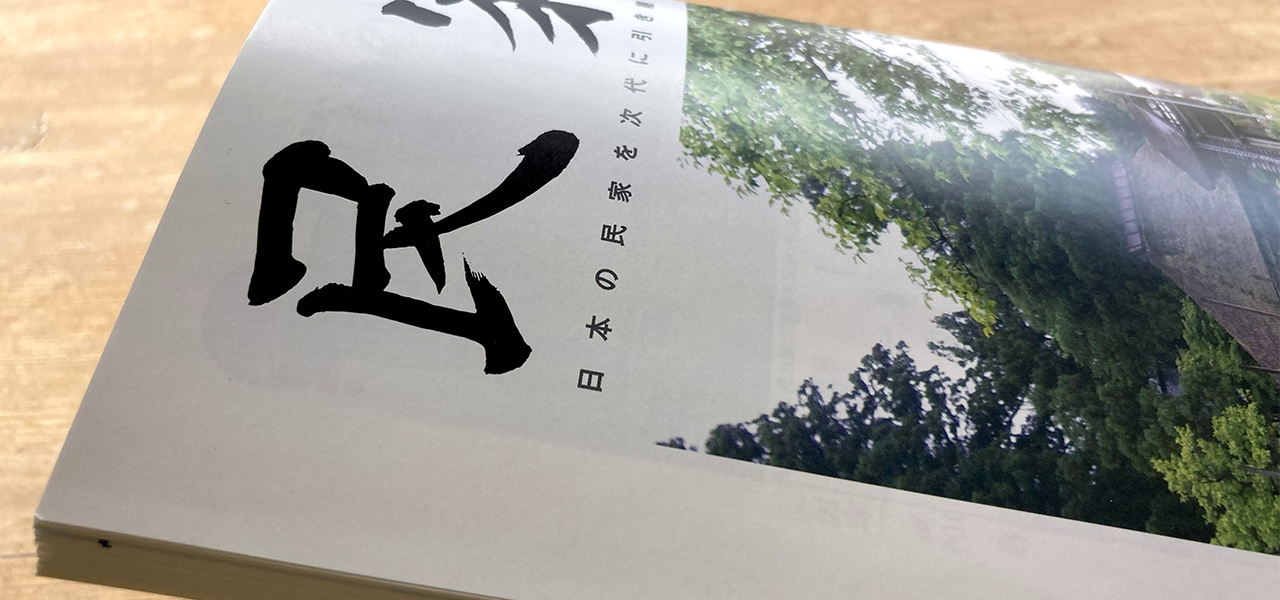
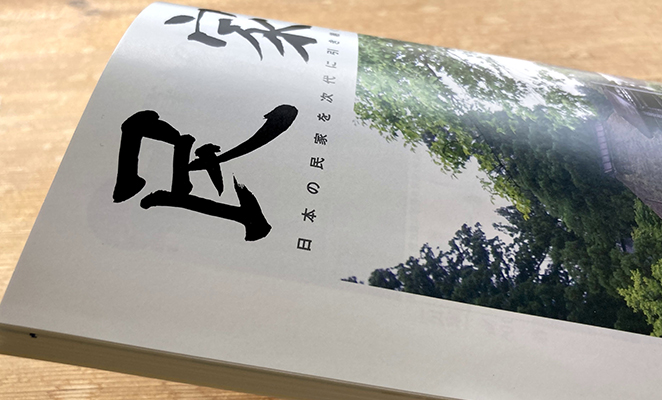
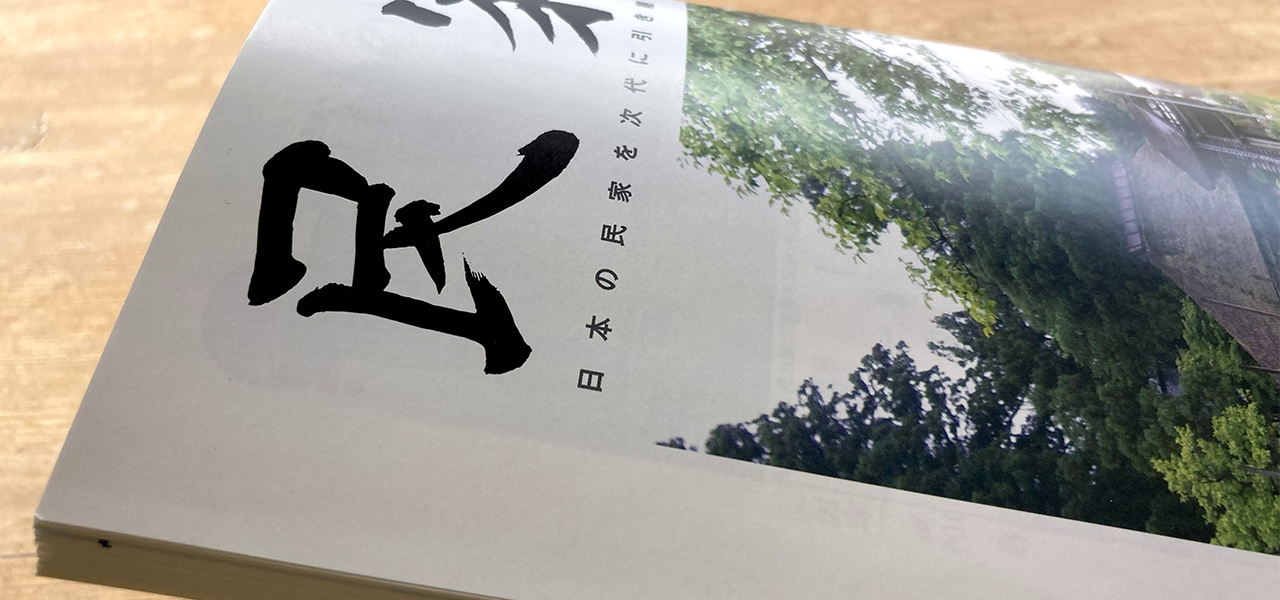
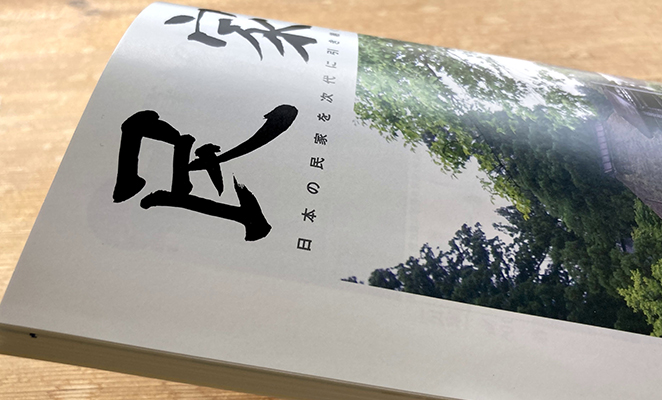
イベントやセミナーに参加したJMRA会員の投稿コーナーです。

2025年8月9日㈯〜10日㈰
山梨県山梨市 参加:15名
民家お助け隊
季節外れの梅雨のような雨が降り続いた8月の連休。三み 富とみの古民家では障子の張り替えと建具の建付け直しが行われました。まずは既存の障子紙を剥がして枠組みをお掃除するのですが、これが大変。重ね貼りされてきた障子紙の年輪が、なかなか剥がれないのです。しかし綺麗にすると、組子の匠の技や木目の美しさが現れました。玄関は透け感が美しい手漉きの落水紙で張り替え。障子を張り替えたお部屋は見違えるほど明るく、柔らかい光が入り込み、美しい空間に生まれ変わりました。 (K.H.)


2025年8月9日㈯〜11日㈪
山梨県山梨市 参加:12名
民家お助け隊
今年は生憎の雨模様でしたが、参加した子どもたちは雨なんてものともせず、全力で楽しんだ3日間でした。
1日目は昨年裏山から庭に移植した苔が定着している様子を確認し、驚くほど冷たい川で泳いだ後は、温泉に駆け込みました。夜は野外で映画の上映会。忘れられない夜になりました。
2日目からは障子張りと外土間の床作り。お決まりの、“張ったばかりの障子が破ける”ハプニングもありました。土間は、土と消石灰と苦にがり汁と最後に少しのタイルで、それはそれは愛着を感じる床ができあがりました。 (Y.I.)


2025年7月20日㈰
長野県上水内郡小川村 参加:20名
信州民家の会
第3回目は山下さん宅の古民家にて開催。江戸時代の名残が見られる趣ある建物内部を見学後、ご近所の河邉さんご夫妻の指導のもと、玄関の土壁に漆喰を塗る作業を体験。漆喰は硬めの方が塗りやすいが、すぐに乾いて広げるには力が必要。一方で柔らかすぎると垂れてしまい、仕上げが難しい。硬さの加減の重要性を教わり、作業を通して実感。昼食はミャンマー出身のご主人によるスパイスの効いたカレーを堪能。イギリスやアメリカ出身の参加者も加わり、異文化が交差する興味深い一日となった。(M.K.)


2025年4月6日(日)
東京都豊島区
石神井公園ふるさと館・旧内田家住宅
参加:37名
桜の花に迎えられた入学式は、 晴れやかな春日となり、今年も民家が好きな大人たちの部活「民家の学校」が開幕しました。
初回の講座は、 木材に触れつつ樹種の違いによる特徴を学ぶ「木のクイズ」に始り、民家の基礎を学ぶ「民家の歴史」「茅葺屋根の歩き方」「旧内田家住宅の見学と移築の解説」 の3講演という構成で、盛りだくさんな内容。
合間に設けた茶話会では、 初対面の受講者も民家という共通テーマで会話に
も花が咲きました。 (R.M.)


2025年3月1日㈯
埼玉県飯能市 参加:12名
まちづくり部会
水と緑の森林文化都市を標榜する飯能市の街中を歩きました。奇しくも街中では「ひな咲くまち」と銘打ったひな飾り展を開催中。 空襲の難を逃れ、かつて山の物と街の物が揃う市には、その店先を貸し出していたという蔵造りの店舗。三島由紀夫の小説『美しい星』に登場する旧郵便局の旧邸。黒竹の生える洒落た人寄せで出迎えてくれる旧うなぎ屋店舗等。都市化の進む街中でも、ひっそりと佇むその建物・風情は後世に残したいものです。(H.N.)
