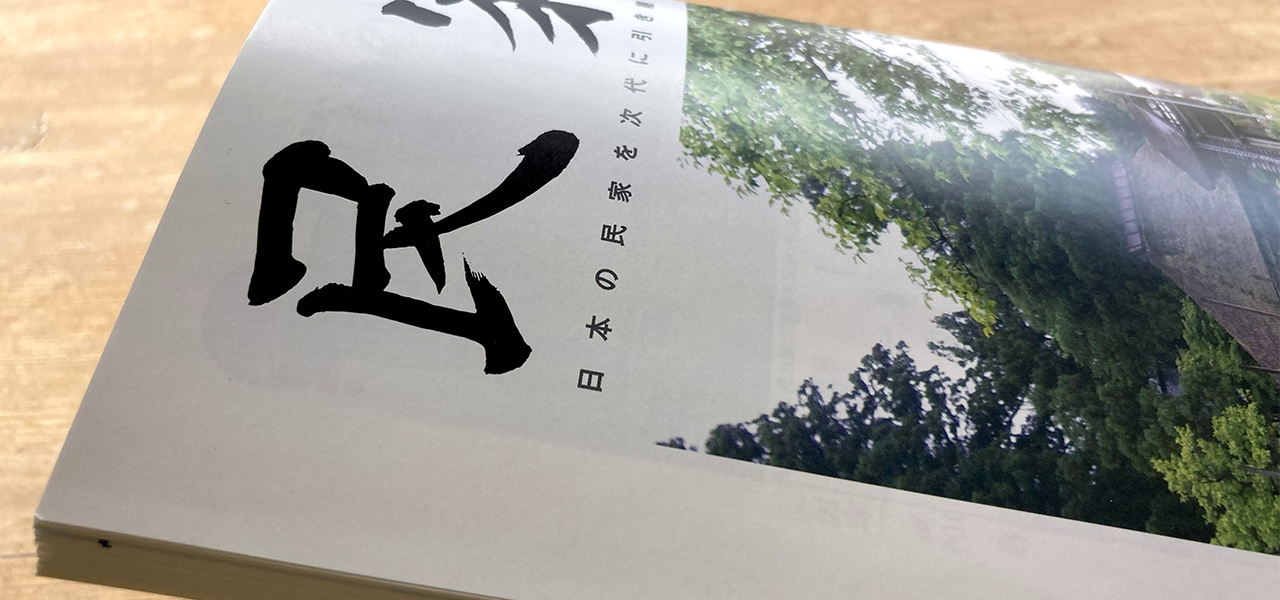
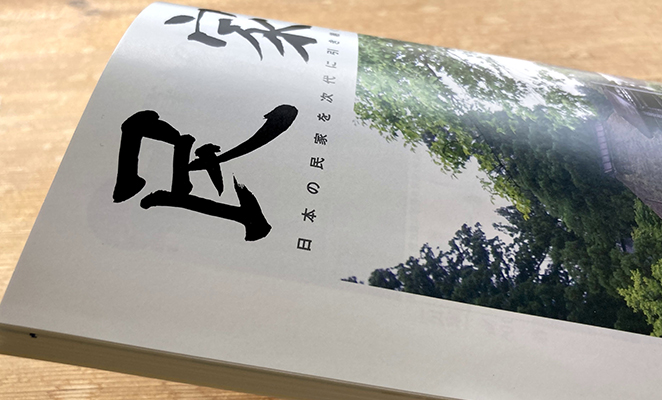
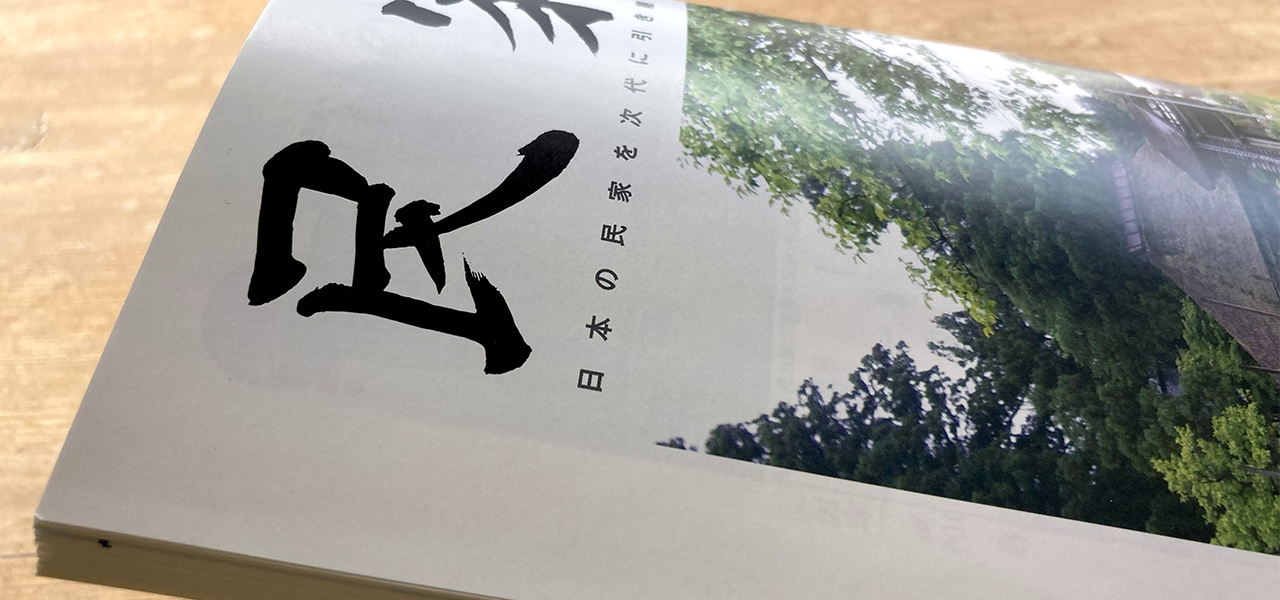
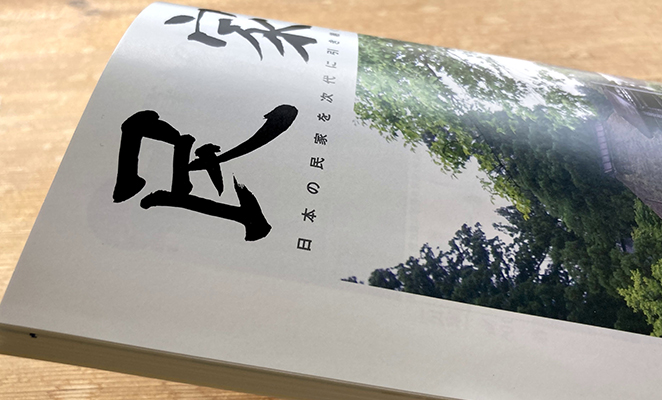
イベントやセミナーに参加したJMRA会員の投稿コーナーです。

2025年8月24日㈰
長野県長野市七二会丙 参加:16名
信州民家の会
第4回目は大塚さん宅の民家にて開催。築100年の民家の2階床張り体験。床板をどのように張るか、参加者で相談しながら、一区画の床を完成させ、おいしいランチの後は、柿渋の仕込み(渋柿をビニールに入れ、木製ハンマーで潰す)と絞り(発酵した渋柿を絞る)を全員で体験。柿渋は予想外に匂いが強くなく、少々発酵した匂いがある程度で、これが防虫・防水に効くと聞き、余った渋柿を持ち帰り壁板に散布。さらに、初参加組は、蔵を改造した現在の自宅も見学させてもらい、私にとっては非常に得るものの多い、交流会となった。 (H.I.)


2025年9月6日㈯
東京都国立市 参加:23名
民家まちづくり部会
甲州街道沿いにある旧本田家住宅の復元工事中の見学会。説明は施工を担当した風基建設の三田様。江戸時代から数回増築・改築され現在に至っており、東京都指定有形文化財(建造物)に指定 された。市の復元方針は本田家の歴史を重ねた昭和34年を想定。柱通り芯も一部ずれていたり、傾いた柱もある中、耐震補強も終わり、古材は70%残している。養蚕の火炉も見つかり、復元するとのこと。金属屋根であったが、茅葺で復元。今後造作・内装・外構工事を行い、竣工は来年夏頃。熱意ある説明で質疑も多く、予定時間かなりオーバー。来年後の見学会が楽しみ。 (T.U.)


2025年9月7日(日)
神奈川県伊勢原市
参加:26名(スタッフ・OBを含む)
昨年に引き続き伊勢原市にて、宮大工の内田棟梁より国宝や重要文化財の建築物や社寺等の修理の仕事、数々の古民家の再生・移築・修理の施工事例などについて講義いただきました。伝統を守りながら、若い大工の方が持続可能なように労働環境や設計過程をDXで整備されている様子も拝見しました。後半は「伝統木造構法」で行う、継手の技術の一つを体験。木材に墨付け、刻み、接合の実技で、この学校で見学する「民家」で用いられる断面部材の木組みの建物が、どのようにつくられているのかを体験しました。匠の技術の素晴らしさ、先人の偉大さを体感した一日でした。(Y.A.)


2025年9月14日㈰〜15日㈪
長野県木曽郡木曽町 参加:7名
民家再生技術部会
木曽地方は木曽ひのきをはじめ良質な木材の生産地です。私達は、御嶽山のふもとに広がる地域の、かつて板葺石置屋根であったであろう本棟造や長屋造の伝統的民家や、その付属屋である数々の板倉を巡りました。杣や大工人口も多い山林地帯は、古くから馬産地として知られ、江戸中期頃からは主屋の2階を蚕室にして養蚕も盛んで、民家はまさに産業と暮らしを物語るものでした。
研究論文のテーマとなった木曽の民家と自力で移築再生中の板倉を中心に、惜しげもなく詳細な解説とご案内をいただいた鈴木湧土さんに心から感謝します。(S.S)


2025年9月20日㈯〜21日㈰
山梨県山梨市 参加:21名
民家お助け隊
ワークショップ会場となった元養蚕農家の2箇所の再生が終了。生活スペースのある古民家らしい姿になってきました。
養蚕室だった上階床の板張りが完成。続いて居住空間だった地上階の元座敷を杉無垢材にした床板張りも完成。根太に補強束を加えて耐重量化しています。ピアノがこの部屋に置かれるそうです。
次回はいよいよオンドル設置に向けて作業が始まります。 (T.M.)
